連休で遊びに来ている孫と一緒に城山に登ってきました。
最近は親抜きで孫だけ遊びにくる(宇都宮駅渡し)ことが多いのですが、今回は息子の家の子供二人。
七歳(小一)、五歳(年中)、ばぁばとじぃじの四人パーティ。
五歳児は段差が大きな箇所で手を引いたり抱っこしたりしましたが、それでも元気よく全員最後まで歩きとおすことが出来ました。
あと、十年もしたら手を引いてもらって登るのかなぁ。
それはそれで楽しいような哀しいような。
っていうか、そもそも相手にして貰えてるのかな😅
連休で遊びに来ている孫と一緒に城山に登ってきました。
最近は親抜きで孫だけ遊びにくる(宇都宮駅渡し)ことが多いのですが、今回は息子の家の子供二人。
七歳(小一)、五歳(年中)、ばぁばとじぃじの四人パーティ。
五歳児は段差が大きな箇所で手を引いたり抱っこしたりしましたが、それでも元気よく全員最後まで歩きとおすことが出来ました。
あと、十年もしたら手を引いてもらって登るのかなぁ。
それはそれで楽しいような哀しいような。
っていうか、そもそも相手にして貰えてるのかな😅
二週間前に腰に違和感を覚えながらも、なんとか快方に向かっていましたが、11日にとある動作をした時にグギっとやっちゃいました。
結局、その前の週より後退したような症状でいささか凹んでいます。
6年くらい前に朝ベッドから起きられなくなった時に比べれば全然マシだけど、やはり起床時はちょっと辛い。
12日から週末までスポーツクラブ通いはお休みしてひたすら静養をしたせいか、幾らか軽くなってきたものの、まだ靴下を履くのが大変です。
立って歩くのはまったく問題ありませんが、腰を曲げる動作(特定の角度のみ)や硬い椅子に座るのが苦行。
腰痛コルセットを巻いて生活しています。
安静より運動していたほうが直りが早いのは今までの経験で実証済ですが、まずは月曜から少しづつ慣らしていかなくちゃ。
軽く運動でもと思い、ここ数年決まったように訪れる羽黒山の蝋梅を今年も見てきました。
神社下まで車で上がるので運動にもならないですが😅
丁度見頃なのかなぁ。良い香りに包まれていましたよ。
神社から山頂経由で一周して、羽黒茶屋でのうどんをいただくのも毎年恒例。
この位の散歩なら腰は全然平気、というよりも血行が良くなってむしろ気持ち良いくらい。
歳を取るといろいろありますが、どこかに行ったり何かをしたりすると、「次があれば良いなぁ」と思う気持ちが段々強くなってきます。

蝋梅の香りに包まれて満足 来年も平和な世の中、そして健康を維持しながら見ることが出来ればよいなぁと思う
撮影使用機材
・NIKON Z50
・NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
・AF-S DX NIKKOR 35mm 1:1.8 + FTZⅡ
珍しく宇都宮にも雪が積もりましたね。
衆院選では高市フィーバーで自民圧勝。
信任を得たからすべて禊が済んだ?でこれでやりたい放題か。
なんだかなぁ。
勝ち組だけが生き残れる、取り返しのつかない日本になるのだけは勘弁して欲しいもの。
冠雪の風景を求めて古賀志山を撮りに行ってきました。
一枚目の古賀志山を南から望む地点では何とマイナス10度。
宇都宮市内ですよ。
集団登校の小学生に元気な声で挨拶を貰いました。
カメラだけぶら下げて月曜の朝からぶらぶらしている老人にも声をかけてくれる子供達。
未来の主役。彼や彼女にどうか良い世の中が訪れますように。
撮影使用機材
・NIKON Z50
・NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
城山の過去の記事
2024年12月25日 山ラー納め
2020年02月24日 これぞ里山
2009年04月19日 今期薮の歩き納め、城山周回
2007年02月11日 まだまだ続く里山巡り
本当はそろそろ雪のある所にと思っていたのですが、忘れた頃に再発する腰の張り(痛み)でちょっと様子見。
ということで、久しぶりに朝活してきました。
歳を取ると早起きは得意になる筈なんですが・・・
いや、確かに布団の中で目が覚める時間は早くなっているけど、寒い中起きだすのとはまた別なレベル。
日の出前に自宅を出発というのも結構気合が要るものです。
ブラックスタートなんて久しぶりだな。
ヘッデンの明かり頼りに、階段だらけの登山道を詰めて30分弱で山頂へ。
三脚設置して設定いじったり、寒いのでお茶飲んだり。
いよいよ日の出ショータイムの始まり。
でも、思ったほどに染まりませんでした。
加えて撮影技術の未熟さよ😭
全ての設定がフルマニュアルでしたが、スマホカメラのほうが奇麗に撮れんじゃね。
まぁ、何事も経験ということで。
終われば楽しい朝活でした。

女峰山カッコイイけど色がうまく出せなくて難しい😣露出アンダーでもいまいちだった

塩谷側ルートは積雪バッチリの模様 山頂南面も登るの大変そうだな😅
コースタイム等データ詳細
YAMAP掲載 https://yamap.com/activities/45960650
山レコ掲載 https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9252316.html
撮影使用機材
・NIKON Z50
・NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

-『スーパー地形』+『カシミール3D』+『国土地理院地図閲覧サービスデータ』にて作成-
雨巻山の過去の記事
2026年01月08日 雨巻山周回不発
2019年01月19日 雨巻山、足尾山から境界尾根
2021年03月10日 今週もまた県境つなぎ
2007年12月24日 2007年、歩き納めの雨巻山
関連山行
2021年03月03日 県境尾根を繋ぐ
前回不発だった雨巻山周回の後半部分を歩いてきました。
高峯登山口駐車スペースに車を置き、ワインレッド号(折り畳み自転車)でいざ出動!
全般的に下り基調なので漕ぐ辛さは一部の軽い上り区間だけ。
まだ日が差し込まない集落の道を走ると、頬に当たる風がことのほか冷たく痛かったです。
深沢下乙公民館にワインレッド号を留め置き登山を開始しました。
地形図実線道がガセ(よくあるパターン)だったら序盤から藪漕ぎ?と思いきや、
しばらくは軽トラの轍も鮮やかな道が続きます。
その先は耕作地だったんですね。
時折地上20cmくらいの低い高さに張られた電柵を幾度か跨ぎます。
私有地内を歩いているのは明らか。
自分で通っていてなんですが、ここはあまり勧められないかもしれませんね。
少し違う箇所からアプローチしたほうが良かったかも。
明らかな道形は途中で行き止まりになりますが、目論見の方角に延びる奇麗な杣道をなおも進みます。
左手の稜線にいずれ乗らなければならないのですが、しばし杣道に付き合うも、間伐の谷で行き止まり。
直登で尾根の芯に乗りました。
ここまで薮らしい藪も無く、順調でした。
そしてなんと、この稜線も実に奇麗で拍子抜け。
たまに小枝が出ているくらいでとても気持ちの良い尾根です。
目的が明確ではありませんが、ピンクテープも多数あります。
登山が目的ならこんなに沢山付けるとは思えないので、山仕事の人の何らかの印かもしれませんね。
途中に記号が書かれたテープも散見されました。
倒木が大量に散乱している箇所をやり過ごすと伐採されたピークへ。
ここは7年前に県道一号線に向かって北上した時に昼飯を食べた場所でした。
当時は樹に囲われていましたが、最近地籍調査があったようで日差しが差し込む明るい場所になっていました。
このピークから先は境界尾根になり、ますます明瞭快適になります。
タイタニック岩から登山者の声が聞こえてくれば、登山道への接合まであともう少し。
予想以上にあっけないルートでしたが、無事予定通り。
おっと、まだ雨巻山を踏んでいないんだっけ。
登山道に入ると沢山のハイカーと行き会います。
山頂のベンチを使わせていただき昼飯としました。
結構寒くて辛かったですが、コーヒーまでのフルコースを楽しみました。
車を置いた場所までは、最後の区間だけちょっとしたバリルートも入れて本日山行の〆としました。
ようやく二回で周回が完結。
本当は一発で歩きたかったのだけど、今の自分の体力気力ではこんなものかな。

耕作地に出るが途中に電柵多数なのでむやみに立ち入らないほうが良いかも

目論見の稜線にうまいこと乗ってくれると思いきや甘くなかった 突き当りで左の斜面を直登

7年前に雨巻山から尾根を北に辿り県道1号線まで歩いた時の休憩地に到達

当時は単なるピークで眺望が無かったが、最近地籍調査があったようで周囲が刈り払われていた

ここから先は境界尾根なので更に快適さがアップ とは言いつつも斜度があがると枯れ葉に難渋

おぉ!時代物だね懐かしい😃メルカリで高値がついていたぞ これで実際に飲んだことある人手挙げて!

タイタニック岩の周りは7年前に比べて木が切られて随分スッキリしていた

そろそろ釈迦ヶ岳と思っているのだが、山頂付近が随分白くなってきたので期待できそう

少し南に進んだ箇所にある展望台も周囲が伐採されて眺望抜群になっていた

屋根が落ちた石祠 木で修繕してあったが、持ち上げるのは相当重いのだろうね

五年前は境界線に固執してここを直進して激藪に絡めとられた苦い思い出 今回は素直に道標に従い深沢峠へ

ここが県境地点で駐車地はこの向こう 眼前の伐採地に取り付くべし

都合よく向かう方角にブル道が伸びている 5年前は左側のピークに登り詰めた
コースタイム等データ詳細
YAMAP掲載 https://yamap.com/activities/45833141
山レコ掲載 https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9226360.html
撮影使用機材
・iPhone 13 Pro Max

-『スーパー地形』+『カシミール3D』+『国土地理院地図閲覧サービスデータ』にて作成-
八丈島登山の後半は三原山(東山)です。
山頂周辺はアンテナ施設が沢山あるので少し興ざめ感もありますが、それでも島を二分するピーク。
登らないで帰るという手はありません。
アンテナ保守用に山頂直下まで舗装路があるのですが、昨年の台風被害で通行出来ない区間があり現在は車で到達することは出来ません。
八丈島観光協会のブログによると、「令和8年1月19日(予定)までの期間、一部区間が終日通行止めとなっております。」とのことです。
初日の観光日に実際に途中まで走ってみましたが、ゲートで堅く閉ざされていました。
また今日現在(1/20)開通の案内はありません。
他にも通行出来ない道路があります。登山等を計画される方は最新情報の取得をお願いします。
この直下地点まで行けば山頂まで僅か数分なのですが、今回は別なルートでアプローチしました。
八丈島一周道路から防衛道路という林道に入ります。
途中も台風で倒れた木などが散乱している箇所があったりしますが、とりあえず通行は可能。
防衛道路から登山口の標識に折れるとその先はすれ違い困難な道になりますが、軽自動車はこんな時には大活躍です。
巨大アンテナ設備の下に僅かな駐車スペースがありそこが登山口になります。
ここに停められなかった場合は、駐車可能なところまで後退してスタートするつもりだったので上首尾です。
アンテナ基部の脇を通り電柱が続く登山道へ。
登山道というよりは電柱巡視路のような感じですね。
鉄塔巡視路階段といえばプラスチック製と決まっていますが、こちらはしっかりと固定されたコンクリート製。
案外歩きやすかったです。
中盤から階段は消え、ひと登りで展望地へ出ました。
八丈富士の美しく広がる円錐形にしばし足が止まります。
下山してきた外人女性と挨拶を交わしたあと自分も山頂へ。
眺望は南側のみでしたが、八丈島のもう一つのピークに立てた喜び。
そして、遥か南方にある小笠原諸島にも夢が拡がります。
いつか、チャンスがあったら行ってみたいなと。
下山時も登ってくる女性一名と交差。
八丈富士は沢山の登山者を見ましたが、こちらは静かな山でした。
下山後は全くのノープラン。
思いつくまま気ままに島を楽しみました。
翌朝、レンタカーを返していよいよ乗船。
島を離れます。
僅か二日間の滞在でしたが、懐かしささえ感じてしまう魅力がある場所でした。
いっぽう、
コンビニやチェーン店など一切なく、便利さとは程遠い生活。
食料品やガソリンなどの必需品だって数割以上高いです。
運賃がかかっているからしょうがないんですね。
時化続きで船が着かなければ、食料品はたちまち店から姿を消すと話されていました。
産業や就労先も限られている島の生活が容易ではないことは想像に難くありません。
自分のような一介の観光者が軽々に言うことではありませんが、
どこかに置き忘れてきたような島の日常にノスタルジーを感じた事は確か。
また、人が少ない筈なのにスーパーに立ち寄れば沢山の人達の笑顔と暮らしがありました。
膨張し続けながら一極集中で格差を作り出す日本社会。
ささやかな経験ではありますが、車中泊を通して地方の中小規模の都市や限界集落を見ながらいつも同じような事が頭をよぎります。
今回も、ちょびっとそんな事を思った旅でした。

防衛道路という名前の林道を通り、最後はアンテナ施設の巡視舗装道を使ってここまで上がってきた

展望地から、先ほど登った八丈富士が裾野を広げる姿が素晴らしい

鈍色(にびいろ)に輝く海が美しい この先にあるのは小笠原諸島 竹芝桟橋から丸一日船に揺られなければ到達出来ない

先ほど歩いてきた電柱巡視路 一番上の電柱からは地下埋設されてこちら側に到達しているようだ

山頂から東に下ると別なアンテナ施設がある ここまで車道が続いているが、現在は台風被害の通行止めで来ることは出来ない

三原山側は結構複雑な地形で、下手に迷い込むと脱出困難な雰囲気あり😱

種類は不明だが暖かさを先取りした桜が咲いていた そういえば八丈富士の登山道でウグイスが鳴いていたなぁ

料理について一通り説明を聞いたが覚えきれない😅 すべて地の物ということで、バナナも自家栽培だという徹底ぶり 滋味ある美味しさに舌鼓を打つ

食後は乙千代ヶ浜へ寄り道 それにしても山体崩壊で凄い景色だね

今でこそ船や飛行機で容易にアクセスできるが、昔はまさに絶海の孤島だったのだろう

乙千代ヶ浜(おっちょがはま)は夏は海水浴場となるが、今は訪れる人も居ない静寂の場所

溶岩海岸の海辺 子供の頃伊豆大島のこんな浜でよく泳いだなぁ 海から上がる時など、よく擦りむいたりしたな

登山の汗を流しに温泉へ 名前の通り露天風呂はオーシャンビューで素晴らしい 観光客比率高め

「むかしのとみじろう」というお店でソフトクリームの明日葉(あしたば)パウダートッピング 明日葉の味は・・・ 正直不明😂

何故か一頭だけ牛が居た 夕日に向かうつぶらな瞳に哀愁の表情(に見えるだけかな)

翌朝、最終日 レンタカーを返しに行く途中で撮影 もうすぐ八時だというのに車も人もまったく見かけない

島の玄関口である底土港前の光景 お店は赤い三角屋根の一軒だけだ

いよいよ出発 便利さとは程遠いけど、のんびりした時間が確かに流れていた 船は辛いけれど、また訪れてみたい場所となった

さぁ、また10時間の船旅 帰りは昼間だから景色もいろいろ期待出来そうだな

ざっと船内を撮影 シャワー室などもある 最上級の個室はホテル並みだが飛行機より高い

船体のデザインを手掛けたイラストレーターの柳原良平氏 トリスウィスキーの絵でおなじみのタッチで描かれた絵が飾られている

食堂は営業時間が限られているが乗船客も極めて少ないので全然混雑しない ベーシックな味のカレーをいただく

食後はチョコモナカジャンボも🍦 甲板で潮風に吹かれながら食べたら流石に寒かったよ😆

のりだすと危ないので手前は撮れなかったが、船側からロープでブリッジを引っ張り上げて固定する

乗客の乗降は無かったが、郵便物の授受やコンテナの積み込み、ケージに入れられた犬?が船内に運びこまれた

三宅島の主峰である雄山は2000年に大噴火を起こしたばかりで頂上付近の白い姿が印象的

伊豆大島も通り過ぎ東京湾近くになると海面も穏やかになる 行きかうタンカーが画になるね

長い船旅と島のゆっくりした時間、素晴らしい景色 心に残る良い旅でした
コースタイム等データ詳細
YAMAP掲載 https://yamap.com/activities/45590728
山レコ掲載 https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9180929.html
撮影使用機材
・NIKON Z50
・NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
・iPhone 13 Pro Max

-『スーパー地形』+『カシミール3D』+『国土地理院地図閲覧サービスデータ』にて作成-
八丈島には北側の八丈富士(西山)、そして平坦地を挟んで南側の三原山(東山)があります。
八丈富士が名前の通り大きな円錐形の山であるのに対し、三原山は割と複雑な山塊です。
これは島の成り立ちと深く関係があるんでしょうね。そんな性格の異なる二つの山に登るのが楽しみです。
他の宿泊者がまだ眠りの中にある早朝、準備を整えて出発。
24時間出入り自由のゲストハウスって、車中泊並みにフットワークが軽いのでお勧め。
さて、登山のほうは今日一日で八丈富士と三原山の両方に登ります。
標高差も共に300m程度の山なので脚力に不安のある自分でも無理はありません。
楽しんで登っていきましょう。
天気のほうは予報通りで晴天。
この時期は爆風が吹くことが多いようですが、今日は風も穏やかです。
八丈富士の山頂お鉢巡りは強風だと危険が伴うということで心配でしたが、歩き始めると時たま5~10m/s程度の穏やかな風。若干北西からガスが流れてくる程度で他は良好です。
7合目登山口駐車場はスペースが限られているため、争奪戦になるということでした。
少し早めに出発したので一番のりで停めることができました。
登山口にある注意事項にクマが無い!
・・・だよね。ここは絶対クマ居ないし。これはすごくリラックス出来るポイント😆
お鉢まではひたすらの階段登りです。
我らが日光の霧降高原にある天空階段に比べればいささか歩きずらいものの、コツコツ登っていけばあっという間に到着です。
荒々しい風景が拡がるお鉢稜線の光景が目に飛び込んできた瞬間、おぉ!と思わず声が漏れました。
一旦火口に向かって浅間神社へと下ります。
一変してこちらは鬱蒼感。
雰囲気がある浅間神社の裏手には、火口底に拡がるジャングルが恐ろし気でした。
この先は行っちゃいけない場所だと、本能的に感じました。
こんなところで藪漕ぎしたら、罰があたって行方不明になっちゃいそう。
外輪山まで戻り、さぁいよいよ、お鉢巡り。
幾らか風が出てきました。
思っていたより気温が高く、心地よい南の島の風を全身に受けながら進みます。
見えるものは火口原と外輪山、海と八丈小島だけ。でも、壮大なジオラマに感動!
果て無き大海原を眺めながらの下山は、いつにも増して軽やかな足取りでした。
後半の三原山に続きます。

未だ充分に光が届かぬ底土港を見下ろしながら車で高度を上げていく

7合目にある登山口駐車場一番Get 路側駐車がおびただしいようで×印で禁止が強調されている

外輪山(お鉢)まではひたすら階段が続く ここは端の平らな部分が歩きやすい

動物除けフェンスがあるが、他の所からいくらでも往来可能で効果ないと思うのだが・・・

昨日行ったふれあい牧場が眼下に ゴマ粒のように牛たちの姿も見える ことねちゃんは元気かな😆

ジグザグだから、反対側の下りは海に向かって降りていくようで爽快
コースタイム等データ詳細
YAMAP掲載 https://yamap.com/activities/45584773
山レコ掲載 https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9179681.html
撮影使用機材
・NIKON Z50
・NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
死ぬまでにやっておきたいこと(ちょっと大袈裟ですが)
島の山に登る。
というか、遠い昔に経験してました。
父親の故郷が伊豆大島だったので、子供の頃は夏になるとよく遊びに行きました。
ある年、珍しく冬に訪れた島、三原山に登ったことがあります。
たまたまの寒波到来がもたらした南の島の珍しい浅雪、一面の溶岩台地に粉砂糖をまぶしたような世界が展開。
白黒の美しい光景に子供心ながら感動した想い出です。
さてさて、そんな紅顔の少年も半世紀以上の時を経て厚顔の老人へ。
子供の頃は「登山って何よそれ」的でしたが、この歳になってみて島の山に登りたい気持がふつふつと湧き上がってきました。
伊豆大島でも良いですが、ここはちょっと頑張って伊豆諸島の南端にある八丈島へ行ってみよう。
伊豆諸島の観光といえばやはり夏が本番。この時期は閑散期です。
また、冬は波が高くて船が接岸できない、あるいはそもそも出航出来ない確率が非常に高く、予定を組むうえでものすごくリスキーな旅になります。
条件付き出航といって、目的地の港に着岸出来ない場合はそこをパスして次の目的地へ、八丈島航路の場合は八丈島で着岸出来ないと、下船しないで東京行便に変わっちゃいます。あるいは三宅島でUターンとか😅
この場合料金は発生しませんが、片道10時間×2の気力体力は確実にロストします。
そんなリスキーな船旅に向けた割引サービスがありました。「スーパー島トクきっぷ」は往復で12,000円。
興味のある方は検索していただければトップで出てきますよ。
通常運賃で片道1万くらいするのでかなりお得。
でも、座席ランクが一番下の二等和室(といえば聞こえは良いが要は雑魚寝)のみで、ランクアップは出来ないルールなのです。
さてさて、はたして無事船は出航して島に上陸出来るのか?
激しい波浪に翻弄されて船酔い地獄にならないのか?
帰りの便が出航出来なくて難民化しないのか?
結果は、万事OKでした。
出発当日の運行予定状況は”条件付き”でしたが、無事定刻に八丈島に着岸。
御蔵島は着岸しなかったけど、この島の着岸確率はかなり低いので有名だそうです。
八人部屋も三宅島に帰る地元の方と二人だけで荷物も手元に置けて広々。
東京湾を出たあたりから波が高くなり結構揺れ始めます。
大した揺れじゃないとは思うけど、横になっても上に下に左に右にシェイクされつづけているといささか辟易。
出力が上がったエンジンの力強い鼓動が床からダイレクトに伝わる。
毛布を二枚(400円)借りて、一枚は下に敷いてクッション替わりにすると結構快適でした。
子供の頃大島に行くのに何度か夜の船で雑魚寝は経験しているし、熱海~大島航路なんて船が小さいので遊園地アトラクションレベルに揺れます。
それに比べれば今の船はなんと快適なんでしょう。
酔い止めを深夜三時頃に追加した効果もあり、吐き気めまいは無し。良かったぁ。
立ち上がると頭はぐらぐらしていて、トイレに行く廊下も揺れで手すり無しには歩けません。
もちろん、用を足すときも手すりにつかまってないと大変な事になりますよ。
まぁ、こんなもんです。超が付くような大型客船以外の船旅は。
早朝五時に三宅島で降りていく方に挨拶をしてからもうひと眠り、気が付いた時は既に日が昇っていました。
定刻通りに着岸していざ上陸。
下船して港に降り立つとレンター会社の方がプラカードを持ってお出迎え。
今回は八丈島の主峰である八丈富士と三原山(伊豆大島にも同名の山があるので紛らわしい)に登ります。
島の滞在は16日と17日の二日間、18日は朝の便(一日一便で来た船が折り返す)で戻るので、登山チャンスは二日間です。
天候やこの時期特有の爆風有無を考慮し、登山予定を組もうと思っていました。
でも、やはり10時間の船旅は疲れるものです。
だめだな。こりゃ。
ということで、島一日目は観光に徹することにしました。
飛行機はどうした?という方もいらっしゃると思いますが、
格安便を探していけば船には及びませんが案外安く行けるかもしれません。
朝一の便で飛び、レンタカーを半日ぐらいで借りて八丈富士にサクっと登る。
どこか有名なところで美味しいランチ、午後の一番遅い便で帰るなんていうのも出来そう。
もっとも、飛行機も強風の時の欠航率は船以上らしいです。
でも、時間だけは潤沢にある年金生活者は全てローコスト、コスパの追及が旅の味わい。
今回もそれを愚直に追い求める島旅となりました。
八丈島はコンビニも無いし、大手資本が経営するチェーンの飲食店などもありません。
民家にちょっと手を加えただけレベルの小さなお店が文字通り”点在”するのみです。
スーパーも二軒だけ。
事前情報でこれを知っていた自分も、いざ島内で行動を始めると切実にそれを感じました。
自販機さえ探すのが大変なほどです。
中心部には幾らか車が走っていましたが、少し郊外に出ると車も人も滅多に見ることはありません。
昨年の台風被害で道路の通行止め箇所などが多く、復旧の途にありますが、やはりこの人口と行政の財政では厳しいものがあるのではと感じました。
今回の宿泊はゲストハウスを利用しました。
二段ベッドに多人数で一部屋、若者グループ向けというイメージがありましたが、泊まったところは個室や二人部屋で快適でした。
チェックインの時に部屋のキーを預けられて、玄関は施錠されていないので24時間自由に使えます。
キッチン部屋に電子レンジ等の設備や食器も常備。
共有のトイレやシャワールームも女性に配慮されていてとても快適でした。
泊まっている人も結構高齢の人が見られ、これからの旅はこんなのもアリだなと感じましたよ。
さて、明日は予報もバッチリ。
風も無く快適な登山が約束されたようなもの。
スーパーで買った島寿司を堪能しながら9%のロング缶チューハイを飲み終えると、深海に沈み込んでいくように意識が遠のいていきました。

夕方の確定状況は条件付き出航となった 八丈島で接岸できずにまた10時間かけて東京へ戻る可能性が残る😥

ターミナルに行っても同じ情報が掲示 果たして上陸は果たせるのか💦

22時10分、いよいよ乗船開始 黄色のカラーリングが鮮やかな橘丸

二等和室(最下ランク) 一番奥がマイブースだが八人部屋で二人だけだったので傍らに荷物を置くことが出来たので広々

船体に合わせてロープまで黄色 いざ出航!ビルの明かりが流れ去っていく

おはようございます 結構揺れたが酔い止めが効いてとりあえず元気 三宅島は無事に着岸したが御蔵島は通過だった もうちょっと早起きすれば日の出が見られたのだが😓

心配もよそに定刻通り無事着岸 10時間の長旅お疲れ様でした>橘丸

レンタカー(右奥の黒い軽)借りてまずは島を一周(数時間あれば可能っぽい)

溶岩の椅子😅 島の中心部以外は走っている車もほとんど無し 北側半周終わるまで自販機さえも無かったよ

溶岩が創り出した荒々しい海岸の向こうに八丈小島の存在感が大きい かつては人が住んでいたらしいが今は無人島

劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』(見てないけど)にも登場したという海辺のベンチ

島南部へ向かう途中 大坂トンネル手前から八丈小島と八丈富士のビューポイント

八丈島のキョンといえば「がきデカ」というあなたは昭和ミドル(笑)

更に進み、ふれあい牧場では三原山をバックに牛がのんびり草を食む

こちら側(八丈富士)とあちら側(三原山)の間の平坦地が生活領域で、そのど真ん中に空港滑走路がある

寄り道した護神山公園にある島酒之碑 島と言えば焼酎だが今回は飲む機会無かった😔

さて晩飯を調達しますかね 品ぞろえが良いと評判の八丈ストアには島唯一の百均も併設

名産の島寿司で夕食 ロングの缶酎ハイが船でヘロヘロになった体に麻酔のように効いてこのあと撃沈
撮影使用機材
・NIKON Z50
・NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
・iPhone 13 Pro Max
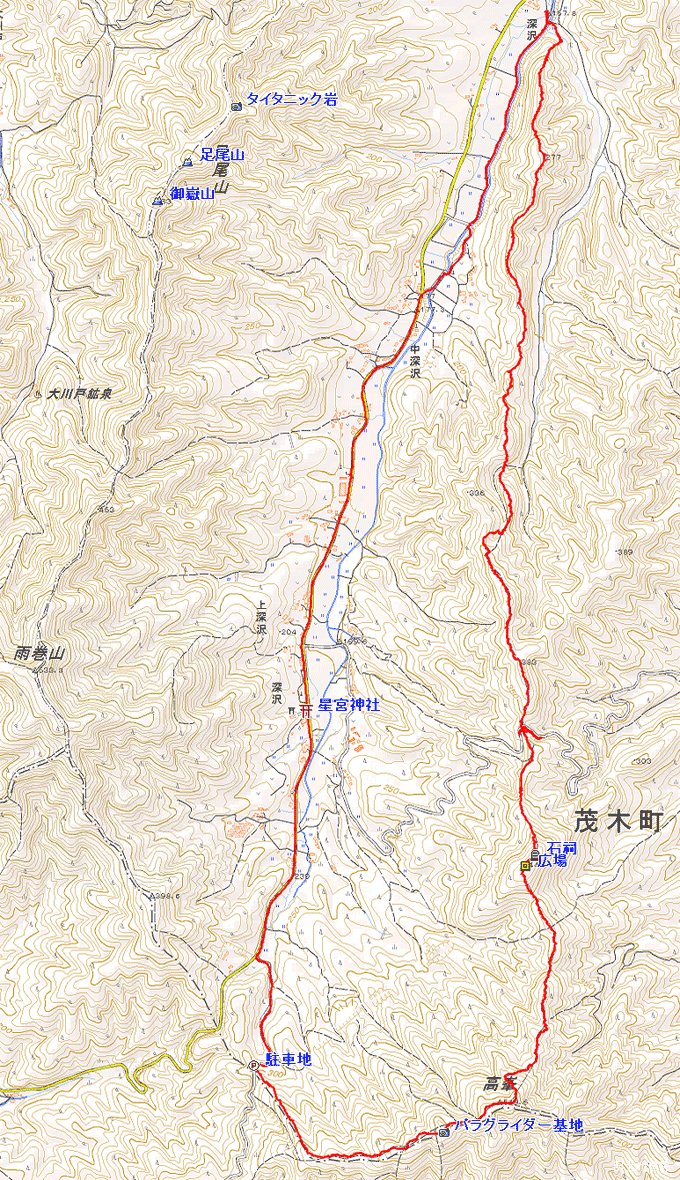
-『スーパー地形』+『カシミール3D』+『国土地理院地図閲覧サービスデータ』にて作成-
-当ルートには一般登山道でない箇所が含まれています。参考にされる場合はご注意ください。-
高峯の過去の記事
2021年03月10日 今週もまた県境つなぎ
2021年03月03日 県境尾根を繋ぐ
関連山行
2019年01月19日 雨巻山、足尾山から境界尾根
そろそろ雪のあるところも歩きたいものですが、ここのところ、北の方面は荒れ気味。
近間の霧降はまったく雪が無さそうだし、釈迦ヶ岳も塩谷側からだとまだ雪が少なそうなのでもうちょい様子見かな。
ということで、今冬の里山遊び第三弾。
高峯から北尾根を降り、深沢集落から県境尾根に取り付き雨巻山へ登り返して周回というプランでした。
北尾根は五年前に全長の1/3を歩いていたのでそれなりに雰囲気は把握しています。
ですが、その先が結構な藪具合でした😓
回避するとルート逸脱、ルート堅持すると激藪といった感じでなかなかペースが上がりません。
途中の車道跨ぎで法面に阻まれて降下出来ないハプニング発生。
降りられそうな場所探しで15分程度タイムロスです。
その後も濃淡ありの藪波状攻撃が続きます。
尾根末端到着予定を11時としていましたが、既に一時間以上遅延しています。
時間切れ+気力切れで後半の雨巻山への登り返しはパスですね。
恐らくそこも藪は避けて通れないだろうし。
藪漕ぎヤッケに着替えるタイミングが遅れ、安ダウンが破け羽毛が少し出ちゃった😭
随分前から、透明テープのパッチだらけだからそろそろ買い替え時期の啓示でしょう😆
後半は長い長い車道歩きでした。
車の元にたどり着いた時は今日の行動予定時間ギリギリだったので、実際に雨巻山を登ってくるとプラス二時間くらいかなぁ。
日没が早いこの時期、16時下山っていうのは嫌だしね。
深沢集落からの雨巻山は次回持ち越し。
高峯登山口から取り付きまで折り畳み自転車でアクセスする予定です。

本日ルート随一の展望 加波山の後ろに筑波山、そして右に目をやると富士山!

結果的には今日踏んだ唯一名のあるピークの高峯へ到着 この時点ではまだ雨巻山まで行く気満々だったのだが・・・💦

正面標柱が目印 右に行くと仏頂山へ、左側は登山道を離脱して北東尾根となる

序盤若干踏み跡に惑わされて想定外の巻きが発生したが、尾根の芯に復帰するとご覧のようなスッキリ

五年前にもその出現に驚いた平坦地 こんな山中に何故?構築物跡の雰囲気もある

お!伐採地だ 右奥の小高いあたりは鶏足山から花香月山方面だと思う

伐採地頂部が想定ルートと一致するからこの区間は楽々歩きでペースも上がる

法面に阻まれて降下点が見つけられず苦労したが、どうにか林道へ着地

初め、この左側に出てしまったが当然降りられず周囲を偵察してようやく先ほどの所で着地 続きは右奥の作業道から入山

五年前はこの星宮神社裏から取り付いて雨巻山へ登ったが、やはり途中は藪含みだった

林道平沢線入口箇所の日陰は部分的に軽くアイスバーン スタッドレスに履き替え済だが朝はちょっと緊張した
コースタイム等データ詳細
YAMAP掲載 https://yamap.com/activities/45424046
山レコ掲載 https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9147300.html
撮影使用機材
・iPhone 13 Pro Max
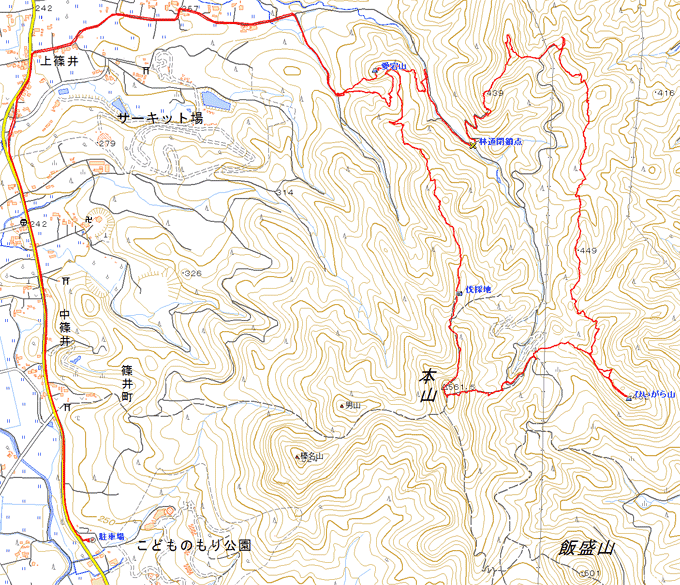
-『スーパー地形』+『カシミール3D』+『国土地理院地図閲覧サービスデータ』にて作成-
-当ルートには一般登山道でない箇所が含まれています。参考にされる場合はご注意ください。-
本山の過去の記事
2024年12月19日 篠井富屋連峰プラスツー
マニアック山行、今シーズンの藪山歩き第二段は、もう何年も前から気になっていた篠井連峰の本山東側エリアです。
取り付きの愛宕神社入口からは二年前に本山の北尾根を下りで歩いたことがあるので、今回はそこを登ります。
本山から東に延びる地形図破線道を下り、東側エリアにある三つの標高点を踏みながら周回という予定を立てました。
本山からの破線道は影も形もなく、一体、いつの時代にどういう風に道が付いていたのかは知る由も無し。
林業が盛んな時代は作業道があったのか、あるいは古い木挽き道(木材搬出用の溝みたいな道)があったのか。
まぁ、これは地形図あるあるで過去に幾度となく経験していること。
今更驚きません。
でも、この下り区間、下るに従い激藪へ。本日の核心部その一でした。
482mP(ひいがら山)からの戻り区間は、想定外にルート模索に手こずったので核心部その二。
そして、439mPから地形図実線道(とは名ばかり)が廃道藪化していて核心部その三。
最後は東から愛宕山へのアプローチ箇所はルート探索するも藪急登からのトラバース。核心部その四でした。
要は殆ど核心部だったということで、今季の累計藪満足度(まだ二回目だけど)はいきなり満タンに近づいた一日でした😁
※こどもの森駐車場から愛宕山登山口までは折り畳み自転車で舗装道、それ以外は本山の山頂から30mの間のみ登山道です。

車道の僅かな上り坂にヒーヒー言いながら最後は押して歩いてようやく登山口へ ワインレッド号はここであるじの帰りを待つ

愛宕山入口と大書してある割には速攻で藪が始まる😅二年前はもうちょっとすっきりしてたんだけどなぁ💦

順調に本山北尾根に乗り途中で伐採地頂部を通過する 正面左奥は羽黒山、右の木が透けているピークが復路で通過する449mPだ

山頂から僅か30m登山道を歩き、ここから地形図の破線道を追うもそんなものはどこにも存在しない😓

目論見の紅白鉄塔を目指し、藪の手薄な箇所を模索しながら進んでいった

すぐに正面の藪が薄い部分から入山 中に入るとすぐに植林帯になり、案外スッキリしていて拍子抜けする

大した藪もなくやすやすと482mPへ到達 なんと!山名あり 早い者勝ちのパターンか?

ルート取りに翻弄されながらも、お次の449mPへ向かう途中の稜線は天国状態

こんな看板あり 26平方米って5m正方形?借受期間も昭和だね😆

真新しいブル道があり少し追ってみたが、すぐに末端に到達して再び入山する

林道を80m程進み再び入山 作業道が右巻きで伸びているが左側のピークへ直接登る

なんと!巡視路階段があった この先450mほどの所にある鉄塔の巡視路のようだ

直接ここへ登り上げても良かったが斜面が急だったので巡視路をそのまま進み、途中から戻って稜線に乗った 日溜りの平坦地、ここでザックを置いて昼食にしよう

439mPには用途不明の標柱があったがおそらく林業に関した所有者境界だと思われる

どうにか地形図実線道に接合するも、既に藪化 これは道じゃないね😅

林道に降り立つ ゲートの先が先ほどの上篠井林道支線終点になる

降りてきた方面はここで舗装が切れているが、航空測量をした時はこの先も道形がはっきりしていたのだろう

登るべき目論見の稜線はあそこなのだが、等高線以上に斜度があって落ち葉も多いので周囲を検討した

藪はうるさいが、比較的登りやすい箇所から高度を上げながらトラバース

今日はルート取りに苦労しまくったが、ようやく最後のピーク、愛宕山へのビクトリーロード

ここから下は参道だが一般登山道比ではほぼ藪山、でも今日の歩きからすれば極楽だ

ワインレッド号を無事回収してこどもの森Pへ戻る途中、振り返ると紅白鉄塔の左下あたりが食事をした場所だな

ワインレッド号は過去のバリエーション山行を沢山支え続けてくれた愛着の一台(リアフェンダー凹んでいるけど😅)

帰りは下り基調なので漕ぐのも楽ちん、先週登った半蔵山が見えた 右側の薄毛ピークが落ち葉急登で絞られた425mP
コースタイム等データ詳細
YAMAP掲載 https://yamap.com/activities/45010450
山レコ掲載 https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9071826.html
撮影使用機材
・iPhone 13 Pro Max